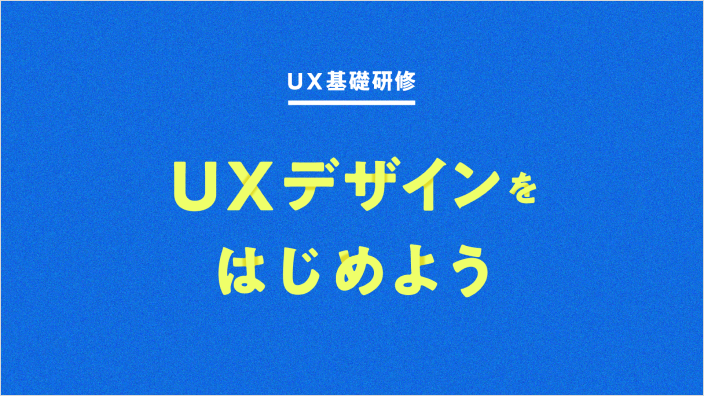UXは専門職だけのものじゃない。カルチャーの橋渡しと仕組みづくり SMBCコンシューマーファイナンスIT戦略部が目指す“自律 × デザイン思考”のチームづくり(2)
- デザイン経営
- サービスデザイン
- UX/UIデザイン
- 教育・人材育成

個人向けローンサービス「プロミス」を展開するSMBCコンシューマーファイナンス(以下、CF)は、2023年4月、デジタル化推進の中核として「IT戦略部」を新設しました。専任のデザイナーチームを置かず、ノンデザイナー中心でデザイン思考を取り入れながら、顧客体験価値を高める新しい組織づくりに取り組んでいます。
本連載では、数回にわたりCF IT戦略部の挑戦を紹介しています。第2回は、長年システム部門で要件定義に携わってきた部付部長・浮田雄介さんに、三井住友銀行(SMBC)から着任しCFのIT戦略部を率いるようになった武井部長のアプローチをどう受け止め、自らの視点や役割を変化させていったのかを伺いました。
▶︎第1回 「“インハウスデザインチーム”を置かないデザイン組織」
▶︎第3回 「自分の答えに辿り着くための『UXガイドブック』」
第1章 システム畑からUXの現場へ
3つの領域をまとめる“翻訳者”
石井:まず、いま浮田さんがIT戦略部でどのような立場・役割なのかを教えてください。
浮田:今期は推進グループを直轄で見ていますが、部署全体も見渡しています。IT戦略部には、社内のユーザー部門の要望をシステムに伝える「要件定義」、UXの視点で付加価値を加える「UX企画」、コンテンツや方針を決める「企画」の3領域があります。これらをつなぎ、部署としての筋を通すのが私の仕事です。
石井:ここでいう“ユーザー部門”は、社外のお客様ではなく、社内でシステムを使う営業や企画などの部署のことですよね。具体的にはどんな部門が含まれ、それらをどう「つないで筋を通して」いるのでしょうか?
浮田:大きくは営業、企画、顧客対応センターなどですね。それぞれ目的が違っていて、営業なら契約獲得、顧客対応センターなら問い合わせ削減や効率化を求めます。だから部門ごとに優先順位をすり合わせる調整が必要になりますし、加えて社内の要望だけを優先するとお客様の体験を損なうこともある。たとえば効率化のためにボタンを減らした結果、逆にお客様が迷ってしまうようでは本末転倒です。
石井:つまり、部署間で異なる目的をすり合わせつつ、社外のお客様の視点も忘れちゃいけないわけですね。
浮田:そうです。そのためには立場ごとの“言葉の意味”や前提を揃える必要があって。同じ言葉でも、ユーザー部門が使う意味とシステム部門が使う意味が違うことはよくあります。長くシステム部門にいたことで、双方の言葉や文化を理解できる。これが間をつなぐ“翻訳者”としての強みですかね。

浮田雄介氏(SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 IT戦略部部付部長)
プロミス株式会社(現SMBCコンシューマーファイナンス株式会社)に入社後、支店、コールセンター等の勤務を経て、2007年より一貫して同社の要件定義に携わる。現在は同社のIT戦略部にてUX企画を所管するとともに、企画を世に出すための要件定義等を含めた体制整備・人財育成を推進。
人を育て、集め、今に至るまで
石井:次に、これまでのキャリアの流れを教えてください。今の役割にどうつながっているのかも知りたいです。
浮田:システム部門で10年以上要件定義を担当しました。転機は2015年の業務システム大改修。当時はユーザー部門に要件定義ができる人はほぼおらず、システム部門が要件定義を作成していました。リリース後結構な数のインシデントが発生しましたが、要件定義をシステム部門任せにしたことが原因だという指摘もいただき、ユーザー部門が自分で要件を出せる体制の必要性を痛感しました。
加川:それは確かに動くしかない状況ですね。そこからどう仕掛けていったのですか?
浮田:当時の自分の部下で要件定義ができる要員をユーザー部門に送り込み、ユーザー部門のメンバーと一緒に要件定義するようにしました。ユーザー、システム双方の現場を知っている人材は強いですし、そのメンバーが今は管理職になって活躍してくれています。
石井:現在は、その人材をIT戦略部に集約していると。
浮田:そうです。集約前はスキルを持った要員が金融・債権管理・保証といったユーザー部門の各部に分散し、人を動かすには人事異動が必要でした。今はスキルを統一しているので、例えば債権管理領域の大型案件に要員追加が必要となったときに、金融担当がサポートにすぐ入れるなど柔軟に動かせます。これまでの経験を振り返ると、私はゼロからつくるより既存をブラッシュアップして良くするのが得意で、それが今の土台づくりにつながっています。
半信半疑で見ていたUXの世界
石井:ここまでのキャリアのお話を聞くと、UXやデザインって言葉は出てこなかったですよね。その領域に触れたのはIT戦略部に入ってからですか?
浮田:そうですね。「IT戦略室」だったIT戦略部創部の前の年あたりから、社内で「UI/UX」という言葉があちこちで飛び交うようになっていました。室が発信していただけではなく、いろんな部署から「UI/UXだー」みたいな声が聞こえてきて。で、正直そのときは「あっちサイドの話なんだろうな」と思ってましたね。
石井:あっちサイド(笑)。今は「UXの視点で付加価値を加える」とUX企画の役割を言語化されていますが、「UX」に対する当時の印象と今の定義にはギャップはありますか?
浮田:ええ。なんかだいぶチャラい話だなって(笑)。
石井:そうですよね(笑)。
浮田:システム部門が長かったこともあって、「まあ好きに言っていればいいけど、ちゃんとつくれるものを考えてくれよ」って思ってましたね。聞こえてくる話も突拍子もないアイデアだったり、「あんなことこんなことやるぞ」みたいなのが多くて。「いや、それどうやってつくるんだよ」っていうのが最初の正直な感覚です。
第2章 ”あっちサイド”の面白さ
石井:最初はUX/UIを「あっちサイドの話」と見ていたとおっしゃっていました。その印象が変わっていくきっかけは、やっぱりIT戦略部での経験ですか?
浮田:そうですね。大きかったのは、武井さんがIT戦略部の部長に着任されたときです。当時の私は業務要件を作成するグループを担当していて、UX企画は別の副部長(当時の役職)が担当していました。自分は自分の領域をきっちりやるつもりでしたけど、武井さんが銀行での経験やネットワークを活かして、CFにも新しいやり方や文化を入れようとしているのを見て、「これは面白そうだから乗っかってみよう」と思ったんです。自分ひとりでは絶対に出てこない発想でしたから。
石井:最初から一緒に動くようになったんですか?
浮田:いや、最初は距離を置いてました(笑)。ただ、案件によっては「背景や経緯を説明してほしい」と声がかかるようになって。そこから少しずつ議論やワークショップに顔を出すようになったんです。
石井:その現場で、何か印象に残ったことがあったんですね?
浮田:はい。ある改修で成果が出た案件があって、そのやり方を聞いたときに衝撃を受けました。開発サイドにいると、私たちはつい「プロダクトが良くないから直す」と考えがちなんですが、UX企画のやり方は違ったんです。お客様が触れる全ての画面を洗い出して、それぞれの場面でユーザーならどう感じるかを検討していた。その上で「じゃあこういう仮説を立てよう」という形に落とし込んでいて。「ああ、こういうやり方をしていたら成果は出るな」と思いました。感性ではありつつ、理屈で説明できるというか、ちゃんと地に足ついたやり方なんだなと。それまで勝手に「ふわふわとやっているんだろう」と思い込んでいた印象とは、違うなと感じました。
石井:以前は夢物語のように聞こえていたものも、実際にはユーザー像や仮説に基づいてロジカルに組み立てられていた、と。
浮田:ええ。それを知ってから「これは面白い」と思うようになりましたし、自分も関わってみたいという気持ちが強くなりました。
石井:面白いなと思うようになってから、関わり方も変わっていったんですか?
浮田:そうですね。担当ではなかったので、システム開発との整合で困ったら声をかけてもらう、という形から始まって。声がかかれば中に入って「ああだねこうだね」とやり取りしているうちに、どんどん関わる場面が増えていきました。
石井:そして翌年にはUX企画を担当する副部長に?(笑)
浮田:そうです。そうなっちゃう(笑)。

石井真奈(株式会社コンセント デジタルプロダクトディレクター/Product Design group チームマネージャー)
デジタルプロダクトと業務デザインのディレクションを得意とし、顧客企業のデザイン組織支援に注力。顧客特性に応じたチームビルディングとマネジメントを推進する。2021年より三井住友銀行のデザイン組織支援にプロジェクトマネージャー・デジタルプロダクトディレクターとして参画。現在は三井住友銀行、SMBCコンシューマーファイナンスの2社を対象に統括PMとしてデザイン戦略を支援。
第3章 仕組みで支えるUX──裏方としての意思決定と設計
いいUXアイデアも、実現できなければ意味がない
石井:以前に浮田さんと話していて印象的だったのが、「UXのアイデアがあっても、すぐに世に出せなければ意味がない」という言葉です。その課題感って、もともとどういうところから来ているんでしょう?
浮田:これは私がシステム部門にいた頃からの感覚ですね。当社は毎年10月頃に、翌年度にシステム開発を希望する案件を各部からエントリーしてもらって、それをシステム部門で工数や優先順位を見ながら採用していって開発計画を立てています。ウェブシステムはこれくらい、基幹系システムはこれくらい……と工数枠が決まっていて、枠が埋まったら翌年度はもう新しい案件は入れられない。10月時点で最長1年半先までの案件をきっちり決めるのは、現実的には無理があります。
加川:たしかに、年度が始まってから方向転換も普通にありますもんね。
浮田:そう。4月に部署のトップが変わって「やっぱりこっちをやりたい」となることもよくあります。でも計画枠はもういっぱいだから、何かと入れ替えない限り新しいことはできない。UX企画から出る案件って、規模は大きくないけど早くやりたいものが多いんですよ。でもそういう柔軟性はほぼなかった。
加川:計画段階で全部埋まっちゃうからですね。しかもその計画が1年半前に決まっているって、変化が激しい今の環境だとかなりの縛りですよね。
浮田:そうです。そこで2022年2月に大規模なウェブシステム刷新をリリースしたときに、「リリース後に改善する工数枠をあらかじめ確保しておこう」ということで周囲と相談して小さく始めました。そうしないと、改善したいときに他案件を削るしかなくなる。結果的にその枠はすぐ使い切ってしまったんですが、この発想をもっと体系化できないかと思ったんです。
加川:それでアジャイル型のチームづくりに?
浮田:はい。もともとうちのウェブシステムを担当していた常駐のシステム開発協力会社さんにも相談して、まずは2022年度に小規模なアジャイルスクラムを試しました。本当におまけ程度の規模感でしたが、その場で発生した課題にすぐに対処できるチームです。これが思いのほかうまくいって、2023年度から基幹系システムや業務系システムが関連する案件にも対応できるよう補助工数もつけて、本格的に始動しました。2024年度は2023年度対比で2倍、そして2025年度は2023年度対比で3倍規模まで拡大しています。ちなみに2025年度は2022年度にお試しした規模の10倍です。
石井:すごいスピードで拡大していますね!
浮田:そうですね(笑)。もちろん課題も見えてきますが、VUCAの時代って言われる中で、1年半前に決めた計画をそのままやるだけでは変化に追いつけない。だからこそ、リアルタイムで状況を見て改善できる“備え”を持つことが大事だと思っています。また、この体制拡大は当部だけではなしえなかったことですので、同じ思いをもって取り組んでもらっているシステム部門にも感謝しています。
現場を動かすための“土台づくり”
石井:UXを良くするために機動性高く動けるアジャイルチームをつくったとのことですが、それを具体的にどう上手く機能させたんですか?今までのプロセスを変えたチームが上手くいくことって、なかなか難しい話だと思うんですよね。
浮田:仕組みだけつくっても動かないので、現場が自分たちで動けるようにする土台づくりが大事です。大きく分けると、3つあります。
①案件共有ミーティングとチームアップ
浮田:案件がスムーズにアジャイルチームに乗るように、当部だけで決めるのではなく、ビジネス部門の各部と合意しながら「アジャイル開発に適した案件」をストックします。その過程で、テーマごとにチームアップも行います。例えば計数面からアプローチするチームや、VOC(お客様の声)をベースに改善を進めるチームなど、目的や課題に応じた編成です。
②自然発生的に生まれるテーマ
浮田:案件のテーマは計画的に全網羅して決めているわけではなく、自然発生的に生まれるものも多いです。離脱の深層追跡チームや、武井さんが「この観点でやりたい」と立ち上げたチームもあれば、各部の活動と合流してできたものもあります。新規申し込みの導線改善チームなんて、いつの間にかできていたくらいで(笑)。私自身、なぜその流れでできたのか分からないケースもあります。
加川:自然発生的にできている感じがいいですよね。普通は一度全部洗い出して、課題をグルーピングして、やる・やらないを判断して割り当て……ってなりそうなところを、そうじゃないのは、逆に何か有機的で面白いなと。
浮田:しかも、こうした柔軟さが成り立っているのは、メンバーと私たちの距離が近い部署だからだと思います。グループ長だけでなく、部の上席陣を巻き込んで直接やり取りできるので、「やってみたい」と言えばすぐ形になる。この距離感は武井さんの方針でもあって、できる限り続けたいと思っています。
③横串で観点を統一
浮田:チームが増えると、観点や判断基準、価値観がバラつきやすい。部門や役割が違えば、なおさらズレやすい。つくるチームが違っても、お客様から見れば同じサービス体験の一部ですから、体験がちぐはぐにならないよう考え方=価値観の軸は揃えておきたい。
私はあまり細かいレビューはしないんですが、「この観点は他のチームと揃ってる?」は必ず確認します。必要があればチーム同士をつないで合わせてもらうこともありますね。
石井:なるほど。価値観の横串を効かせて、運用で整えているわけですね。では、その価値観って、具体的にはどのように違うのでしょうか?

加川 大志郎(株式会社コンセント プロデューサー/プロジェクトマネージャー)
システム開発寄りのウェブディレクターからキャリアをスタートし、15年以上ウェブサイトの構築・運用プロジェクトに従事。ウェブ情報アーキテクチャに軸足を置き、数十~百を超えるウェブサイト群のガバナンスやウェブを中心としたデジタルマーケティングに関するコンサルティング、プロジェクト推進を得意とする。事業計画におけるウェブ領域の役割定義から、日常のオペレーション業務の効率化までをトータルでコーディネートできる守備範囲の広さが強み。近年はウェブサイト運営を導入にしたDX推進やマーケティング組織開発支援、デザイン人材育成支援に領域を拡げている。
第4章 感性とロジックのあいだに立つ──翻訳者の役割
システムとUXの価値観の違い
浮田:例えばインシデント対応のときですね。新しいプロダクトを導入していく中で思った通りの仕上がりではない等のトラブルは必ず起きます。そのときシステム部門はやはり「要件の漏れなのか、不具合なのか」という点にこだわりが出ます。ユーザー部門からすると「いや、出せるなら出そう、出せないなら直そう」でいいじゃんって思うんですけど(笑)。私も長いことシステム部門にいましたので理屈はわかりますけど、守っているものが違うなと感じます。
だからユーザー部門が「これは要件の漏れだと認めない」と突っぱねるようなことが起きる。でもそんなところで争うのは不毛じゃないですか。ただ一方で、システム部門が「必要なものは全部直します」と言ってしまったら、安定した品質は保てないし、納期も守れない。それもわかる。
なのでユーザー部門側もゴリ押しするのではなく、「どうしても必要なものだけは直したい」というスタンスでいないといけない。一度「これでいく」と決めたら、その責任は持つ。信義則みたいな話ですが、それが守られないとシステム部門も「じゃあ無理です」と自分を守る方向に振れてしまうんです。
石井:なるほど。対立の構図はどういうケースが多いですか?
浮田:ユーザー部門+IT戦略部 vs システム部門、っていう線が引かれることが多いですね。どこで漏れたかはともかく、最終的にシステム部門が受け取るのは要件定義なので、「要件に漏れがあった」という話になる。だから起案したユーザー部門とIT戦略部の間に価値観の違いがあるわけじゃなくて、システムとの間に線が引かれる感じなんです。
価値観も言葉も違う世界をつなぐ
石井:今のお話を踏まえると、まさに翻訳者が必要になる場面ですよね。浮田さん自身は、実際どうやって「翻訳」しているんですか?
浮田:やっぱり一番は、額面どおりに受け取らないことですね。「この人は本当は何を言いたいのか」を取りに行く。文字通りに受け取るとズレることが多いので。
要件定義の書き方でもそうで、システム部門に渡すときは“解釈の余地がない”ところまで書くべきと思っています。逆にユーザー部門とのやりとりは、あえて曖昧さを残したほうが動きやすい。きっちり詰めちゃうと、そもそもアイデアが出なくなっちゃうんで。
石井:ルールで固める部分と、曖昧さを残す部分。その塩梅を見極めてるんですね。
浮田:うちの部員にも「両方に対応できなきゃダメだよ」って言ってます。システム部門はルールがガチッとしてる方が動きやすい、ユーザー部門は逆に曖昧さがあった方が動きやすい。その違いをちゃんとわかった上で、振る舞いを変えないといけない。
だから相談に来たメンバーが「これってこう書いてあるからこうですよね」って言ったら、「いやいや、そうじゃなくて。多分言いたいのはこっちだから、もう一回聞いてきて」って返すこともよくあります。受け取った文字そのままじゃなくて、背景とか文脈までちゃんと取りに行こうって。
石井:なるほど。浮田さんは、それぞれが使う言語を理解しているからこそ、「その人たちのカルチャーにはこういうブレがある」「こういう価値観で動いてるから、そこを取りに行きなさい」と伝えられているんですね。めちゃくちゃ重要なポジションだなぁ、すごい翻訳者っぽい。
加川:それって実は、社内の関係者のUXをデザインしているのと同じだと思うんです。自分をインターフェースにして、部門ごとに異なるインセンティブを持った人たちと接するときに、その“顧客”を知る。そういう発想に通じてるなと。難易度が高いですけど、まさにIT戦略部ならではの役割ですね。
デザイナーではないがUXを翻訳できる理由
石井:ここまで「翻訳者」という言葉で、浮田さんが立場や価値観の違いをつなぐ役割を担っているお話を伺ってきました。面白いのは、その中で「デザイン」や「デザイナー」という言葉はほとんど出てこなかったことです。
ただ武井さんを見ていてもそうですが、CFでは必ずしもデザイナーではない立場の人が、デザインの価値や効力を理解した上で、それを武器として使いこなしている印象があります。武井さんはデザイナーではないけれど、限りなくデザイナーに近い存在だと私は思っていて。
そういう方と一緒に動く中で、デザインのバックグラウンドがない浮田さんはどんなポジションを取って支えたり、武井さんが目指す部署や構想を実現するためにどう関わってきたのか。そのあたりをお聞きしたいです。
浮田:そうですね、私はデザインの基礎教育を受けたわけじゃなくて、ずっと“ものづくりの現場”でやってきた人間なんです。ただ、どうせ世に出すならいいものを出したい、という感覚は昔から強く持っていました。だから、UX企画のメンバーが考えたアイデアをちゃんと世に出せる形にしてあげるのが自分の役割だと思ってます。体制を整えるとか、段取りを整えるとか。要件定義に体験の視点を乗せて、実際に実装できるようにする。そういう縁の下の仕事ですね。
レビューのときも、専門的なデザインルールというよりは、「一般ユーザーとしてどう感じるか」を重視します。「これ、迷わない?」「ここ、引っかからない?」と一歩引いて確認する。案件に没頭すると見えなくなる部分を、引いた視点で指摘できるのは自分の強みかもしれません。
石井:まさに翻訳者としての経験が生きているんですね。
浮田:そうかもしれません。突き詰めて考えるのは得意な人に任せて、私は「普通の人が見たらどう感じるか」を常に意識する。結果として、感性(体験)とロジック(要件やルール)のあいだで、どちらの言語もわかる人として動ける。そこに自分の存在意義があるんじゃないかと思ってます。

“デザイン”は専門家だけのものか?──言葉の再翻訳
石井:武井さんの記事を書いたり、浮田さんとお話ししてきて、改めて感じていることがあります。「デザイン」という言葉をどう扱えばいいのか?と。
皆さんが日常的に使っているのは「UX企画」や「UX」という言葉ですよね。「デザイン」という言葉はあえて使っていないように見える。ここに込められた意味を、きちんと理解したい。
加川:たしかに。デザイン会社の我々の目線だと、世の中では「デザイン」という言葉を前に出して市民権を獲得しようとする動きも強いんですよね。経産省が「デザイン経営」宣言を出したり、経営にデザインを取り込もうという流れがある。だからあえて「デザイン」と言い続ける人もいる。その一方で、CFのように「デザイン」をあえて使わないことで誤解を避け、地に足をつけるやり方もある。両面があるのが面白い。
浮田:そうですね。武井さんは言葉の定義にものすごくこだわりがある方なので、「UX企画」という言葉を選んでいるのはあえてだろうなと思っています。事業会社であるCFの社内で「デザイン」と言えば、どうしても「見た目を整えること」と誤解されがちになる。そうなると「なんだ、絵をきれいにするだけか」と思われかねない。
でも我々がやっているのはそうじゃなくて、体験を軸に企画することであって、だからこそ「UX企画」という言葉をあえて選んでいる。体験ドリブンでいくんだ、という武井さんの意思表示が込められた言葉なんだろうな、と勝手に想像してます(笑)。
石井:なるほど。例えば「UXデザイン」という言葉を使うと、どうしても専門職の匂いが強くなる。でも「UX」だけだと自分ごとに引き寄せやすいというか。ビジネスの現場で「UX」という言葉が持つ意味って、そういう“届きやすさ”にもあるのかもしれないですね。
加川:「UX」は体験全体を含む分、組織に浸透しやすそう。ただ、広いがゆえに、専門外の人からすると「自分がどこまでやっていいのかな」と戸惑う側面もありそうです。「UX企画」なら、体験を起点に“企てる”という態度が前に出て、広さを担保しつつ、実務の射程にも収められる。言葉選びが秀逸ですね。
浮田:そうですね。部長である武井さんがこういう組織にしたいと思いを込めたことを、私は私しかできないことでうまく流れるように思いをちゃんと汲み取っていきたい。
加川:まさに浮田さんがこれまでやられてきたことですよね。翻訳といっても、単なる言葉の置き換えではなく、文脈を繋いでいく活動。だからこそ「UX企画」という旗印の意味が強くなるし、キーフレーズとしての重要さが際立つ。武井さんが掲げたその旗を、浮田さんが繋いでいく。お二人の出会いが、こう考えると奇跡的な組み合わせだな(笑)。
浮田:そうかもしれない(笑)。
加川:そういう翻訳者とか伝道師とか、言葉を使って人と人を繋いでいく役割って、実はすごく重要なのにあまり取り沙汰されない気がするんです。だからこそ、浮田さんがされていることは独自に意味のある取り組みだと思います。その上で思う翻訳には、僕の解釈では大きく三段階あるんです。
- 1.まず、同じ言葉でも人によって意味が違う部分を正しく理解する。
- 2.次に、解釈の違いを超えて文脈を一致させる。
- 3.最後に、それらを束ねて「じゃあ、こっちだ」と方向を示す。
前半の二つは仲介者でもできます。でも三つ目は、翻訳者自身が意思を持っていないとできない。ここが一番難しくて、でもIT戦略部という特性を踏まえると、メンバーが持っていなければいけない大事な部分だなと感じます。
第5章 内発するUXを育て、その先へ
UXは一部門の専有物ではない
石井:価値観や言葉の違いを繋ぐ役割がIT戦略部にあるという話でしたが、こと「UX」という言葉を取ると、本来はIT戦略部やUX企画の中だけで閉じる話じゃないと思うんですよね。
浮田:そうですね。私たちも「UXを知っているシステム」と、「現場寄りのUXの目」の両方を増やしたいんです。どっちかじゃなくて両方。
それで、顧客対応センターに行って、ある場面を切り取ってワークショップをする取り組みを去年も2回とか3回とかやりました。課題を出して、案件にするところまで持っていく。目的は二つで、一つは当部だけだと目線が偏るので顧客対応を実際に行っている人に入ってもらって新しい示唆を出すこと。もう一つはこの考え方を、普段そういう仕事をしていない人にも広げたいっていう狙いです。
石井:事業の垣根も関係なく?
浮田:はい。今は保証の担当だから金融はわかりません、ではなくて、1ユーザーとして普通に使う人の感覚で考えたらどうかという話なので横断でいいと思ってます。体験をどう考えるかを一度でも経験してもらうのが大事で、面白いと思って一緒にやりたいって人が増えたらさらにいい。
加川:単なる“巻き込み”じゃなくて、同じ道具で話せるようにするって感じですよね。センターの方にも喜ばれますし、短いワークでも考え方の手触りが残る。
浮田:そうなんです。社内向けにはIT戦ニュースというウェブ社内報で観点の発信もしていますけど、読んだだけでは変わらない。やっぱり触ってもらうのがいちばん効く。短時間でも、「こういうふうに考えるんだ」を身体でつかんでもらえると、次の会議での言葉の選び方が変わります。
石井:現場と一緒に取り組むと、どんな意識の変化が見えてきますか?
浮田:典型は「注意書きを書いてくれ」っていう発想からの転換ですね。お客様が選択肢を間違えてクレームが来ると、さまざまなところから「ここに注意書きを足してほしい」って要望が出やすい。でも注意書きなんて読まれないんですよ。
結局それは「言い訳のための注意書き」になってしまう。そうじゃなくて、そもそも間違わない動線に変えることを考えよう、という方向に持っていきたいんです。
石井:UXやCXを履き違えてしまうケースもあるんですね。
浮田:そうなんです。リスクヘッジと体験がごっちゃに語られていることが多い。体験の価値としては、注意書きを足すことじゃなくて、迷わず進めるように設計を変えること。ワークショップで実際に手を動かして「ここで迷う」「戻るのが怖い」って体感してもらうと、みんなの意識がそっちに切り替わっていくんです。
加川:リスク対応として注意文が必要なときはあるにしても、それを“最適解”と誤認してはいけない。「必要なときの苦肉の策」だっていう自覚を持つことが大事ですよね。
浮田:だからワークショップを通して、「注意書きじゃなくて動線改善だ」という思考を経験してもらう。そうすると、その後の会議でも「ここは注意文でいいのか?」「動線を変えられないか?」っていう言葉の選び方が変わるんです。
緩やかな線路と北極星
石井:ここまでお聞きしてきたのは、UXを他部門に広げていく取り組みでした。あらたまって、IT戦略部そのものをどう残していくかに目を向けたいと思います。
浮田:いずれ武井さんも私もいなくなるその時に、IT戦略部のアイデンティティがしっかり残っていてほしいと思っています。今の30代前後のメンバーがすごく頑張っているので、彼らがこの先を引っ張っていけるようにしたい。今大事にしていること、新しく取り入れてきたことをうまく融合させて、また新しいIT戦略部をつくっていけるといいなと。
石井:そういう意味では、私たちと一緒に作ったUXコンセプトも継承のためのツールになりますよね。IT戦略部が顧客に提供したいUX品質を言語化して、みんながそれを一つの北極星として動き始めている。
浮田:そう、緩やかな線路をつくってあげるという話です。向かい方向は人それぞれなんだけど、そこにはちゃんと軸が通っている。最後に目指す北極星は、みんなが共通認識を持っている。

CFのUX企画メンバーとコンセントで練り上げたUXコンセプト。プロミスというブランドがユーザーに提供したい体験を、3つのコンセプトと原則で定義している。
石井:緩やかな線路をつくってあげるって本当に重要ですね。どこまで定義したら緩やかでいられるのか、すごく難しいことだと思います。
加川:ガチガチにしすぎても駄目なんですよね、きっと。
浮田:そう。行動を規定するものじゃなくて、考え方のよりどころ。絶対にこうである、という話ではなくてね。
加川:次のステップとしては、その緩やかな線路を引き継げる人をつくっていくことも必要ですよね。
浮田:それはすごく思います。急に人を集めてきた部署なので、まだまだ頼りない部分もある。CF全体の年齢構成は釣鐘型で、私の世代から上下3年くらいの方は結構多いんですけど、IT戦略部は真逆で若手が多い。だからこそ引っ張っていく世代が足りていない。下が増えれば増えるほど、その上でリーダーとして引っ張っていく人を育てなきゃいけない。人を育てるっていうのも、私の大事な役割なんだろうなと思います。
加川:浮田さんの場合、単発で人を育てるというより、組織がこうあるべきだというビジョンがあって、そのためにこういう人がいたらいいという絵を描いているように見えます。ピンポイントで「この人を」ではなくて、全体の循環を見据えて要所要所に人を配置している。そこが実はデザインの発想に近いと思います。
浮田:全員と私が直接つながっているわけではないですけど、チームや仲間の中で役割を担えるキーマンがいて、その人が周りにふわっと広げていく。そういうことは常に考えています。
加川:プロダクトを出すことに加えて、そのプロダクトを生み出す組織や仕組みまで含めてデザインしている感じですよね。
浮田:むしろ今の私の役割はそっちがメインだと思っています。今日はどちらかと言うと対お客様のUXやものづくりの話に寄りましたけど、基本的に私は手を動かす立場ではないので、手を動かす人たちがパフォーマンスを出せるように組織をグルーピングしたり整えたりする。それが私のミッションだと思っています。
加川:つまり、緩やかな線路をつくって、その線路を延ばし続ける人を育てていく。そしてさらにその先を見据えているわけですね。
浮田:そうですね。行き先は北極星ですから、いつか空を飛ばなきゃいけない(笑)。そんなパラダイムシフトを起こしてくれる人が、いつか出てきてくれたら嬉しいです。
翻訳者としての未来
石井:今日のお話を振り返ると、「緩やかな線路を敷く」「次を育てる」っていうのは、まさに翻訳者の役割にも重なっていると思いました。世代や価値観の違いをつなぎ、同じ方向に向かうように整えていく。
加川:単なる言葉の仲介ではなく、文化や思いを束ねて未来に渡していく翻訳。IT戦略部の活動そのものが、それを体現している気がします。
浮田:ありがとうございます。大げさに言うつもりはないですが、結局はそういう人たちが増えてくれれば組織はもっと強くなっていく。私もその一助になれればと思っています。