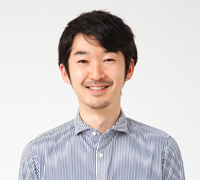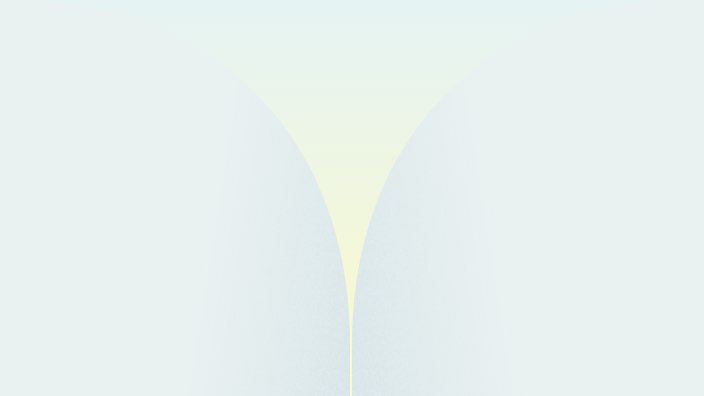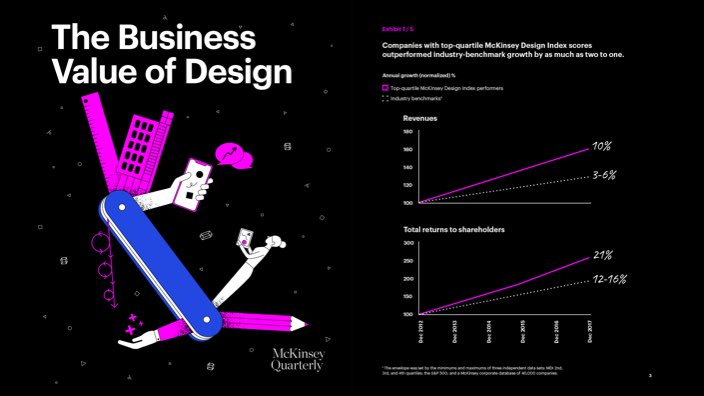【対談|バックグラウンド編】長谷川敦士 × 宮嵜泰成「『デザイン』をはじめたきっかけ」 CONCENT×PIVOT Night Session 2017 イベントレポート
- コンセントカルチャー
コンセントとグループ会社のPIVOTは、2016年4月18日と21日の2日間、就職活動生向けのイベント「CONCENT×PIVOT Night Session 2017」を共同開催。プログラムの第一部で、コンセント代表取締役でインフォメーションアーキテクトの長谷川敦士と、代表取締役社長の宮嵜泰成による「社会に果たすデザイン会社の役割」と題したトークセッションを行いました。

当日は、文学部やシステムデザインマネジメント研究科、商学部、コンピュータサイエンス、経済学部、教育学部というようにいろんなバックグラウンドの学生の方々に参加いただき、長谷川と宮嵜からも参考としてそれぞれが「デザイン」にたどり着くまでのバックグラウンドをお話ししました。本記事ではその内容をご紹介します。
Index
バックグラウンド1:長谷川敦士(コンセント代表取締役/インフォメーションアーキテクト)
バックグラウンド2:宮嵜泰成(PIVOT代表取締役社長)

長谷川:
大学の学部時代は物理学科にいて素粒子物理学をやっていました。
素粒子物理学というのは、物が一番小さくなったときの構成要素を研究対象とする分野のことです。後にノーベル物理学賞を授賞することになる、スーパーカミオカンデ(東京大学宇宙線研究所が岐阜県飛騨市神岡町の神岡鉱山の地下 1000mに設置した素粒子物理研究のための観測装置。コトバンクより引用)のプロジェクトがあるんですが、今から20年くらい前、ちょうどその発見をした頃にプロジェクトをやっていました。
「物が一番小さくなると何がわかるんだろうか?」ということを知りたいという欲求で、大学院の修士課程でも素粒子物理の研究を続けていたのですが、そのうち「物が一番小さくなっても何だかよくわからない」ということがよくわかって。正確に言えば、物が一番小さい状態というのは数式で記述はできるんですけれども。ただ、それが僕の中で直感的に「あ、わかった」ということに結びつかないということがわかったんです。そうして興味をもち始めたのが「人間の脳みそは何をやっているんだろう」ということでした。
人工知能の分野は今でこそ流行っていますが、僕が大学院生の頃の90年代は「冬の時期」と呼ばれ人工知能が下火になった時期。そんな時代のなか人工知能の研究分野に移って、そこで認知科学と呼ばれている研究をやりました。
院を合わせて9年間くらいずっとそうした研究をしていたのですが、2000年になるぐらいのときに、「物事を理解するということのデザインをする」という分野があることを知ったんですね。きっかけはリチャード・ソール・ワーマンというアメリカの編集者です。もともとは建築家でその後グラフィックデザイナーになり編集者になった人です。
NHKで放送されていたりするので知っている人も多いと思いますが、TEDカンファレンス(以下、TED)を生み出したのがこのリチャード・ソール・ワーマンです。
「TED」は「Technology, Entertainment and Design」の略で、TEDのWebサイトには、TEDのロゴの脇に「Ideas worth spreading」(広げる価値のあるアイディア)ということが書いてあります。彼が「これからの時代、“テクノロジー”と“人を楽しませること”と“デザイン”のアイディアは集めて共有することがすごく大事になる。いろんな人たちのアイディアを集める場をつくれば知の共有ができるだろう」とやり始めたことなんです。余談ですが、TEDは1993年に日本で開催されたことがあり、呼んだのはコンセントの取締役である吉田望。彼がリチャード・ソール・ワーマンのファンで電通時代に呼んだんです。
リチャード・ソール・ワーマンは『Understanding USA』(1999年。Ted Conferences)というおもしろい本を書いていて、統計データはそのままでは読みにくいのでわかりやすくするために、アメリカの統計白書を片っ端からインフォグラフィックスにする、ということをこの本でしているんですよね。こうしたプロジェクトを彼はガンガンやっていて、彼の他にも、アクセスマップやガイドブックをつくったりなどいろんなことをやっている人がいる。
彼らの考え方や活動に触れ、こうした意味での新しい「デザイン」という仕事は、美大出身ではない僕でもできる可能性があるんじゃないかと思ったんです。冒頭でもお話ししたように、このような新しい「デザイン」の分野はこれからすごく重要になると思って始めました。

長谷川:
科学のバックグラウンドがあって、リチャード・ソール・ワーマンの「物事を理解することのデザインには、これから可能性がすごくある」という言葉に興味をもち今デザインをやっているわけですが、もう1つ忘れもしないきっかけが『Powers of Ten』という映画です。
映画の冒頭に、公園で人が寝ているところからカメラがどんどんズームアウトしていくというシーンがあります。
英語の「Power」は「○の何乗」というときの数字の肩につけるものを指すので、映画のタイトルの「Powers of Ten」というのは「10の何乗」という意味です。最初が10の0乗だから1mスケールで人が映っているのだけど、10の1乗になると10mスケールになり、次は10の2乗…という具合にどんどんカメラがひいていく。すると地球が丸ごと入り、そのままひいていくと太陽系が入りさらに太陽系が小さくなっていって銀河系に入っていくというふうにどんどんどんどんひいていくのですが、27乗ぐらいまでいくと今度はガーッと寄っていって人のスケールになる。そして10のマイナス1乗になり10センチのスケールになって人の手の中にどんどん入っていって、10のマイナス20乗くらいまでいくと。
このように科学への興味やいろんな視点を得ることにすごく役立つ映画なんですが、IBMと一緒にこの映画をつくったのが、有名な家具デザイナーであるチャールズ&レイ・イームズ夫妻。
プロダクトを手がけていたイームズ夫妻が、人にどうやってものを伝えていったらいいかということや、自分が見えている世界をいかに描いて伝えようかといったことをすごく考えて、コンセプトをつくっているんです。
この映画が制作されたのは1968年で、まだ素粒子というものは一般的には知られていない時代。「ここから先はまだ明されていない未知の世界である」みたいなことで話が終わって。小学生のときにこの映画を観て「わ! その先はなんだろう?!」と思ったのが、僕がそもそも物理をやるきっかけでした。
映画自体がすごくおもしろくて、大きさにとらわれないでいろんな視点で物を考えるということの一助になると思うのでぜひ見てもらいたいです。
今思えば、チャールズ&レイ・イームズ夫妻のデザインされた世界の中で僕は自分のモチベーションを培っていったので、「デザイン」に始まって今また「デザイン」をやっているんだなと感じています。

宮嵜:
長谷川さんはアカデミックな世界で生きてこられていて研究の場に長く身を置かれていたんですけど、僕は全く対極の道を歩んでいて、すごく早い段階で社会に出ています。
今はアプリやWeb サイトをつくっているという会社にたまたまたどり着いていますが、初めに入社した会社で仕事をしているうちに、コンピューターが会社に浸透してきたのがそもそものきっかけです。ちょうど90年代の終わりぐらいですが、インターネットに接続するということ自体が普通の中小企業にとっては「そんなの必要なの?」という時代。そんな時代に「これ、おもしろいんじゃないかな」と思って、自分で勝手に勉強を始めて、だんだんとそういう道に来ているんですね。
そのとき一番おもしろいと感じたのは、その道具の使い方を正しく知りさえすれば、たとえば仕事が10分の1ぐらいの効率になったりしたことです。今はそこまでのドラスティックな変化を起こすことはできるとはいえ難しいですが、当時はその使い方さえ理解すればものすごい効率化が図れることがわかった。勝手に社内を啓蒙・説得して予算をつけてもらってといったことをやっているうちに、どんどん本業になってきたという流れです。
初めは小手先のテクノロジーに踊らされますが、「正しく使う」とか「きちんと効率化しよう」ということに向き合っていくと、「効率化をするためにはどうすればいいか」「そもそもこの業務はどういう仕組みになっていて、なぜこういうルールで動いてるのか」といったことをだんだん考えるようになってくるんですよね。現場の表面的なことよりももう少しさかのぼって、「そもそもなんでこうなっているのか」といった本質的なことをしっかり考えるのが大事。「デザイン」という言葉についても、見た目だけの話ではないということに、やっているうちに気づいていきました。
PIVOTがAZグループに参画する前、コンセントの長谷川さんは僕にとっては先生みたいな感じだったんですよね(笑)。著書などを読んで「こういうふうにきちんと考えて取り組んでいくのが、これから大事だな」と感じていて。そういう情報をキャッチしていたら、たまたまですけれども最終的に出会って今は一緒のグループにいるという。

当日は、文学部やシステムデザインマネジメント研究科、商学部、コンピュータサイエンス、経済学部、教育学部というようにいろんなバックグラウンドの学生の方々に参加いただき、長谷川と宮嵜からも参考としてそれぞれが「デザイン」にたどり着くまでのバックグラウンドをお話ししました。本記事ではその内容をご紹介します。
(バックグラウンド以外のトークセッション内容は、別記事【対談】長谷川敦士 × 宮嵜泰成「デザイン会社が社会に果たすべき役割とは」にてご紹介しています。ぜひ合わせてご一読ください。)
Index
バックグラウンド1:長谷川敦士(コンセント代表取締役/インフォメーションアーキテクト)
バックグラウンド2:宮嵜泰成(PIVOT代表取締役社長)
バックグラウンド1:長谷川敦士(コンセント代表取締役/インフォメーションアーキテクト)
「理解のデザイン」に興味をもったきっかけ

長谷川:
大学の学部時代は物理学科にいて素粒子物理学をやっていました。
素粒子物理学というのは、物が一番小さくなったときの構成要素を研究対象とする分野のことです。後にノーベル物理学賞を授賞することになる、スーパーカミオカンデ(東京大学宇宙線研究所が岐阜県飛騨市神岡町の神岡鉱山の地下 1000mに設置した素粒子物理研究のための観測装置。コトバンクより引用)のプロジェクトがあるんですが、今から20年くらい前、ちょうどその発見をした頃にプロジェクトをやっていました。
「物が一番小さくなると何がわかるんだろうか?」ということを知りたいという欲求で、大学院の修士課程でも素粒子物理の研究を続けていたのですが、そのうち「物が一番小さくなっても何だかよくわからない」ということがよくわかって。正確に言えば、物が一番小さい状態というのは数式で記述はできるんですけれども。ただ、それが僕の中で直感的に「あ、わかった」ということに結びつかないということがわかったんです。そうして興味をもち始めたのが「人間の脳みそは何をやっているんだろう」ということでした。
人工知能の分野は今でこそ流行っていますが、僕が大学院生の頃の90年代は「冬の時期」と呼ばれ人工知能が下火になった時期。そんな時代のなか人工知能の研究分野に移って、そこで認知科学と呼ばれている研究をやりました。
院を合わせて9年間くらいずっとそうした研究をしていたのですが、2000年になるぐらいのときに、「物事を理解するということのデザインをする」という分野があることを知ったんですね。きっかけはリチャード・ソール・ワーマンというアメリカの編集者です。もともとは建築家でその後グラフィックデザイナーになり編集者になった人です。
NHKで放送されていたりするので知っている人も多いと思いますが、TEDカンファレンス(以下、TED)を生み出したのがこのリチャード・ソール・ワーマンです。
「TED」は「Technology, Entertainment and Design」の略で、TEDのWebサイトには、TEDのロゴの脇に「Ideas worth spreading」(広げる価値のあるアイディア)ということが書いてあります。彼が「これからの時代、“テクノロジー”と“人を楽しませること”と“デザイン”のアイディアは集めて共有することがすごく大事になる。いろんな人たちのアイディアを集める場をつくれば知の共有ができるだろう」とやり始めたことなんです。余談ですが、TEDは1993年に日本で開催されたことがあり、呼んだのはコンセントの取締役である吉田望。彼がリチャード・ソール・ワーマンのファンで電通時代に呼んだんです。
リチャード・ソール・ワーマンは『Understanding USA』(1999年。Ted Conferences)というおもしろい本を書いていて、統計データはそのままでは読みにくいのでわかりやすくするために、アメリカの統計白書を片っ端からインフォグラフィックスにする、ということをこの本でしているんですよね。こうしたプロジェクトを彼はガンガンやっていて、彼の他にも、アクセスマップやガイドブックをつくったりなどいろんなことをやっている人がいる。
彼らの考え方や活動に触れ、こうした意味での新しい「デザイン」という仕事は、美大出身ではない僕でもできる可能性があるんじゃないかと思ったんです。冒頭でもお話ししたように、このような新しい「デザイン」の分野はこれからすごく重要になると思って始めました。
映画『Powers of Ten』で広がった未知の世界への興味

長谷川:
科学のバックグラウンドがあって、リチャード・ソール・ワーマンの「物事を理解することのデザインには、これから可能性がすごくある」という言葉に興味をもち今デザインをやっているわけですが、もう1つ忘れもしないきっかけが『Powers of Ten』という映画です。
映画の冒頭に、公園で人が寝ているところからカメラがどんどんズームアウトしていくというシーンがあります。
英語の「Power」は「○の何乗」というときの数字の肩につけるものを指すので、映画のタイトルの「Powers of Ten」というのは「10の何乗」という意味です。最初が10の0乗だから1mスケールで人が映っているのだけど、10の1乗になると10mスケールになり、次は10の2乗…という具合にどんどんカメラがひいていく。すると地球が丸ごと入り、そのままひいていくと太陽系が入りさらに太陽系が小さくなっていって銀河系に入っていくというふうにどんどんどんどんひいていくのですが、27乗ぐらいまでいくと今度はガーッと寄っていって人のスケールになる。そして10のマイナス1乗になり10センチのスケールになって人の手の中にどんどん入っていって、10のマイナス20乗くらいまでいくと。
このように科学への興味やいろんな視点を得ることにすごく役立つ映画なんですが、IBMと一緒にこの映画をつくったのが、有名な家具デザイナーであるチャールズ&レイ・イームズ夫妻。
プロダクトを手がけていたイームズ夫妻が、人にどうやってものを伝えていったらいいかということや、自分が見えている世界をいかに描いて伝えようかといったことをすごく考えて、コンセプトをつくっているんです。
この映画が制作されたのは1968年で、まだ素粒子というものは一般的には知られていない時代。「ここから先はまだ明されていない未知の世界である」みたいなことで話が終わって。小学生のときにこの映画を観て「わ! その先はなんだろう?!」と思ったのが、僕がそもそも物理をやるきっかけでした。
映画自体がすごくおもしろくて、大きさにとらわれないでいろんな視点で物を考えるということの一助になると思うのでぜひ見てもらいたいです。
今思えば、チャールズ&レイ・イームズ夫妻のデザインされた世界の中で僕は自分のモチベーションを培っていったので、「デザイン」に始まって今また「デザイン」をやっているんだなと感じています。
バックグラウンド2:宮嵜泰成(PIVOT代表取締役社長)
現場出発で身をもって実感しながら本質に気づいていった

宮嵜:
長谷川さんはアカデミックな世界で生きてこられていて研究の場に長く身を置かれていたんですけど、僕は全く対極の道を歩んでいて、すごく早い段階で社会に出ています。
今はアプリやWeb サイトをつくっているという会社にたまたまたどり着いていますが、初めに入社した会社で仕事をしているうちに、コンピューターが会社に浸透してきたのがそもそものきっかけです。ちょうど90年代の終わりぐらいですが、インターネットに接続するということ自体が普通の中小企業にとっては「そんなの必要なの?」という時代。そんな時代に「これ、おもしろいんじゃないかな」と思って、自分で勝手に勉強を始めて、だんだんとそういう道に来ているんですね。
そのとき一番おもしろいと感じたのは、その道具の使い方を正しく知りさえすれば、たとえば仕事が10分の1ぐらいの効率になったりしたことです。今はそこまでのドラスティックな変化を起こすことはできるとはいえ難しいですが、当時はその使い方さえ理解すればものすごい効率化が図れることがわかった。勝手に社内を啓蒙・説得して予算をつけてもらってといったことをやっているうちに、どんどん本業になってきたという流れです。
初めは小手先のテクノロジーに踊らされますが、「正しく使う」とか「きちんと効率化しよう」ということに向き合っていくと、「効率化をするためにはどうすればいいか」「そもそもこの業務はどういう仕組みになっていて、なぜこういうルールで動いてるのか」といったことをだんだん考えるようになってくるんですよね。現場の表面的なことよりももう少しさかのぼって、「そもそもなんでこうなっているのか」といった本質的なことをしっかり考えるのが大事。「デザイン」という言葉についても、見た目だけの話ではないということに、やっているうちに気づいていきました。
PIVOTがAZグループに参画する前、コンセントの長谷川さんは僕にとっては先生みたいな感じだったんですよね(笑)。著書などを読んで「こういうふうにきちんと考えて取り組んでいくのが、これから大事だな」と感じていて。そういう情報をキャッチしていたら、たまたまですけれども最終的に出会って今は一緒のグループにいるという。
対談日:2016年4月18日、21日
※本記事は2日間の対談内容をもとに構成したものです。
- テーマ :