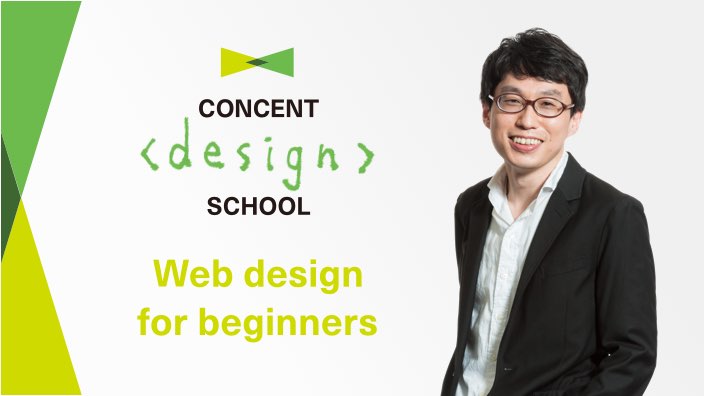世界最大のデザイナーの祭典「ミラノサローネ」 Milano Design Week 2019 イベントレポート(1)
- コミュニケーションデザイン

イントロダクション
コミュニケーションマネージャーの河内です。
コンセントに入社して丸11年になりますが、これまで毎年「IA Summit」や「Service Design Global Conference」などの海外カンファレンスに出かけてきました。
「IA Summit」(今年からは「IA Conference」へと名称・体制とも変更になっています)では、ほぼ毎年コンセント社のIA(情報アーキテクチャ)やUXのメソッドやツールを紹介するようなポスター発表をしたりしていますし、昨年はコンセントの広報でもあり、そしてパーソナルスタイリストでもある私が、ファッションという一見「センスの世界?」と思われる領域において、IAをどのように応用できるのかを説明する「HOW TO MAKE SENSE OF MODE」というポスター発表もしてきました。
「Service Design Global Conference」に関しては、初めて行ったのが2011年ですから、日本でまだ「サービスデザイン」という言葉が浸透していない、そしてコンセントの中にも「サービスデザイン事業部」など存在していない頃の話です。そうしたカンファレンスで見聞きしてきたことを日本に持ち帰り、日本でサービスデザインコミュニティーが立ち上がり、コンセント社内の組織の移り変わりが起こり…と、そうした流れを見てきたことになります。
So what’s next!?
それを見たくなって、カンファレンスではないものに今年は行こうと思いました。
そこで選んだのが「Salone del Mobile.Milano」、通称「ミラノサローネ」(2019年4月8日〜14日開催)です。
この「ミラノサローネ」に、コンセントから私と、アートディレクターの見野、高橋の3名で行ってきました。2回に分けてレポートします。
厳密に言うと「ミラノサローネ」ではないのですが、そのあたりも含め「ミラノサローネ」がどのようなものなのかをご紹介していきます。
ミラノサローネなのか、ミラノサローネではないのか

デザインに関わる仕事をしている人であれば、おそらく名前ぐらいは聞いたことがあるであろう「ミラノサローネ」。
正式名称は「Salone del Mobile.Milano(サローネ・デル・モービレ・ミラノ)」で、毎年春にイタリア・ミラノで開催されている、国際家具見本市です。
「国際家具見本市になぜ、インテリアデザインの会社でもないコンセントが行くのか?」と聞かれるので、より詳しく説明していきます。
この国際家具見本市は、ミラノ郊外にあるRHO FIERA(ロー・フィエラ)と呼ばれる、見本市会場(日本で言えば東京ビッグサイトのようなところ)にて、世界中の名だたるインテリアブランド、家具メーカーがブースを出展します。

東京ビッグサイトのようなところ、と説明しましたが、展示会場は東京ドーム11個分、幕張メッセの2.8倍とも言われており、出展に関しては各ブランドのブースとも、路面店を1つつくるぐらいではないかと思われるほどの規模感とつくり込みで展開します。
今年の出展者数は2,418。また、公式発表されている今年の来場者数は、181の国から38万6,236人でした。


家具の見本市ですから、当然、インテリアメーカーや建築家、テキスタイルデザイナー、家具デザイナーといった人たちが多く訪れます。
しかし、それだけで「ミラノサローネ」はこれほどまでに、世界中の多くの人たちに、そしてインテリア業界以外の人たちにまで知られるようになるものでしょうか?
そこには「Fuorisalone(フォーリサローネ)」と呼ばれる別のイベントの存在があります。
これは「Salone del Mobile.Milano」期間中に開催されるもので、見本市を訪れる「ミラノサローネ」関係者目当てに開かれるようになったとも言われており、見本市会場ではなく、ギャラリーやショップ、空き倉庫や貸しスペース、路上など、ミラノ市内のさまざまな場所で、ある意味自主的に展開される、展示や体験型のイベントの総称です。
こちらは、家具やインテリアに限らず、世界の著名な企業や中小企業、教育機関といったさまざまな出展者により、ファッション、アート、プロダクト、都市デザイン、アバンギャルドなものまで、さまざまな種類のデザインが出てくる展示となっています。
そして、この「フォーリサローネ」と前述の見本市会場で開催される「Salone del Mobile.Milano」とが合わさって、「Milano Design Week(ミラノデザインウィーク)」を構成します。

こうして「ミラノデザインウィーク」には、あらゆる分野のデザインが一同に会し、インテリア業界に限らず世界中から多くのデザイン関係者たちが押し寄せ、100万人規模の人々で賑わうのです。

デザインは多くの場合、関係性や相対性、時代性などを踏まえて検討するものであって、対象物以外も認識しておかなければ適切なデザインはできません。それゆえ、ありとあらゆる広い分野に関する見識が必要ですが、ミラノサローネでは短期間に、そして一気に、世界中の多くのデザイン、文化、感覚、思考にふれることができるため、忙しいデザイナーにとっては大変効率的に情報収集やネットワーキングができる場となっています。
「デザイン業界においてもっとも重要なイベント」と位置づけられているのも、もっともなことです。
ちなみに、会話のなかで「ミラノサローネに行くんだ!」と言う場合、特にインテリア業界外のデザイナーたちがそう言う場合には、「ミラノデザインウィーク」全体のことを意図していることが大半で、「フォーリサローネ」中心に見て回る人も多く、本丸であるローフィエラで開催される「Salone del Mobile.Milano」には足を運ばないという人も多数います。
今回は初参加だったので、全体感を把握するため本会場にも足を運びましたが、基本的には「フォーリサローネ」を中心に回りました。それゆえ、コンセントのメンバーが参加したのは厳密には「ミラノデザインウィーク」の方が適切ですが、本記事では便宜上、通例通り「ミラノサローネ」として話を進めます。
行く前から主体性が必要な「ミラノサローネ」
カンファレンスの場合、カンファレンスチケットを購入し、カンファレンスホテルもしくは推奨されているホテルの予約をし、カンファレンス会場に行って、レジストレーションさえ済ませてしまえば、あとは席に座っているだけでセッションを受講できます。
「せっかく行くのにそれではもったいない!」と感じてしまう私は、冒頭でお話しした通り、カンファレンスでの何かしらの発表やネットワーキングにも努めますが、日本から参加する多くのカンファレンス出席者がそうとは限りません。カンファレンス会場とホテルが同じ場所というケースも多く、極論すると、せっかく海外にいっても、事前準備なしに、また現地でも完全に受け身な態度でもカンファレンス参加は成立してしまいます。
そこがカンファレンスとミラノサローネとの大きな違いです。
ミラノサローネの場合、行く前から大きな壁が立ちはだかります。
それは「一体どこに宿を取るのか?」ということ。
「そんなこと?」と思うかもしれませんが、カンファレンスと違って、ミラノサローネの場合、まずはここに行けばいい、といった見当が全くありません。
そのわりに見どころが大変な量に上るということだけはわかっているため、効率的な移動を考えたいところです。そのため、ミラノサローネ初参加者にとっては、宿を取るところからハードルがあります。ミラノに土地勘がない場合はなおさらです。
「見たい出展者の展示エリアの近くに宿を取ればいいではないか」
と思う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、そこがとても難しいのです。
ミラノサローネの開催は4月初旬ですが、出展者情報は3月に入ってからでないと公開されません。
アンテナを高くしておけば、内々には「○○社は出展するらしい」という情報を小耳にはさむこともありますが、Webで一般的な検索をしてもヒットするのは去年以前の情報ばかりです。
ミラノサローネには100万人規模の来場があり、インテリア業界などはすでに社をあげて、ホテルごと、あるいは数十部屋単位で1年近く前から客室を押さえ始めます。
ですから、年明けの1月頃にはすでに多くのホテルが満室となり、空室のあるホテルでも通常時期の3〜5倍と思われるような室料が提示されます。
また、社内決裁を通している2週間程度の間にも、そうした空室はどんどん埋まり、航空券の価格も倍ほどになってしまいます。
早くホテルを取らなくてはいけない。しかし、その時点では一切の情報がない。
行く場所の見当がついていないなか、そしてそれほど土地勘のない場所で、それでもできるだけいい条件で宿を抑えるということはかなりハードルが高い話です。
ちなみに、ミラノサローネ(本会場)自体のチケット販売サイトでさえもなかなかオープンにならず、販売開始となったのは、オープニングまで軽く1ヶ月は切った後でした。
予約サイトのインターフェースがあまり親切でないこともあり、販売開始になっているのかいないのかさえよくわからず、しばらくの間は不安に感じましたが、例年、販売開始時期自体が遅いようでした。
チケット販売が開始された後も「アクセス集中等によりサイトにうまくつながらなかったり、購入プロセスの最後までうまくたどり着けないこともままある」そうで、平日を避けて週末にアクセスするといった工夫が必要になることもあるとの話も聞きました。
開催の半年や1年近く前から登壇者情報が着々と公開され、アーリーバードチケットなどが販売されるカンファレンスとは大違いです。
ですから、出張が確実にわかっているインテリア業界の方ならともかく、一般的なデザイン会社においては、社内上申するのに十分な情報が揃うカンファレンスとは異なり、なんだかよくわからない手探り状態で社内決裁を通さなければならないという難易度の高さがあり、コンセントのような柔軟で懐の深い会社だからこそ行けたという風にも感じます。
それでも出張ですから、できればより多くの、そして精度の高い情報を集めておく必要があります。
そこで、あらゆるツテを使って、過去に行ったことがある人、出展予定企業などへコンタクトをとり、現地でスムーズに見て回ることができるよう、できる限りのことをしておきました。業界内に閉じていない、普段のネットワーキングと人脈はこういうときに生きるのだと痛感!
現地についてからの動き方を事前に想定しておくことや、変更があった場合の臨機応変さ、現地での情報収集能力など含め、主体性が大変重要になります。そして、デザイナーとしての社会性が問われるのがミラノサローネです。
話題の展示が多いフォーリサローネ
今年の「フォーリサローネ」は、950のロケーションで、876のブランドと1,285名のデザイナーが参加し、1,348のイベントが開催されました。
先に述べたように、フォーリサローネは街中のいたるところで展開されていますが、その多くはいくつかの代表的なエリアに集中しています。
Zona Tortona(トルトーナ地区)、Brera(ブレラ地区)、Ventura Centro(ヴェントゥーラ チェントロ=市内中心部)、Porta Garibaldi e Corso Como(ポルタ・ガリバルディとコルソ・コモ地区)、Porta Venezia(ポルタ・ヴェネツィア)などです。
「今年のミラノサローネで話題になった…」などと紹介されるような展示というのは、基本的にこの「フォーリサローネ」で展開されます。また人気の展示は数時間並ぶようなものもあります。
どのエリアも道を何気なく歩いていれば「フォーリサローネ」の展示会場に行き当たりますが、特にトルトーナ地区には、「SuperStudio」と「OPIFICIO 31」という大きな2つの会場があり、特にSuperStudioには日本企業の出展も多いため、必ず訪問する場所になります。
SuperStudioでは、入り口で事前登録の有無を確認されるため、オンラインで事前登録しその控えをプリントして持っておくとスムーズです。
なぜミラノサローネへ出展するのか?
インテリアブランドによる本会場(ローフィエラ)への出展はともかくとして、フォーリサローネに出展する企業や団体にはどのような意図があるのでしょうか?
いくつかの出展社に話を聞いてみたところ、以下のような理由がありました。
- 1.桁違いに多くの人に見てもらえるということ
- 2.ミラノサローネ出展を前提に社内コンペなどを行うことで、通常のプロジェクトでは出てこない発想が出てくること
- 3.来場者の意識が高く検証のための議論ができること
- 4.ミラノへ行くということ自体がデザイナーのモチベーションであること
- 5.サローネ常連出展者同士においては切磋琢磨し合い、デザイナーネットワークを強固なものとするということ
フォーリサローネの場合、いかによい立地の展示会場を押さえるかということが重要になりますが、このスペースと出展者を結びつけるSpacemakers社とのミーティングの機会を得たので、こちらでも話を聞いたところ、Spacemakers社はスペースマッチングだけでなく、グローバルなメディア対応も請け負っていることから、BBCを始め各国のジャーナリストへのアクセスがあり、広告・宣伝効果が高いとのこと。
例えばLEXUSは、ミラノサローネが契機となってヨーロッパで認知度が上がりブランドが確立した歴史がある、という話も聞きました。
ミラノサローネに行く意義
カンファレンスの場合、セッションの多くは、すでに出ている書籍やブログ記事がベースになっていることも多く、そこをあたれば、カンファレンスに行かずとも、実は趣旨がある程度わかるというものも多々含まれますが、ミラノサローネは一回性のものが多い。このことだけでも現地に赴く十分な価値があります。
また、「魅せる」ことやコミュニケーションデザインのスケールが圧倒的に違います。
プロジェクトにおいては当然、メディア特性による制約やビジネス的な制約などさまざまありますが、思考実験するためには枠からはみ出して考える必要があります。
トルトーナ地区の「OPIFICIO 31」は、「SuperStudio」のホールに出展しているブースと比べて、スペースの多様さも手伝って自由度が高いものが多く、そうした展示を見ていると、「自分たちが普段やっていることを、もしミラノサローネで表現するとしたら何ができるだろう? そのために誰とどんなふうに組んだらよいだろう? あるいはミラノサローネで発表するに足るような仕事を普段しているだろうか?」と想像するいい機会になりました。
どこを見て回っているときでも「このブース、もっとこういう魅せ方をしたら、より意図が伝わったのにな…」とつい分析してしまうのは、コンセントの職業病でしょうか…。
そして、現地では他社や他業界の方との会食の予定も入れていましたが、そうした会食、そして現地で突発的に誘っていただいた会食などを通じて、話題の展示の関係者と知り合えたり、裏話を聞けたり、滞在中に行くべき展示などについて情報収集することもできました。
いずれにせよ、膨大なインプットができるとともに、全くの更地から考えるようなダイナミックさと柔軟な発想をもつための、通常業務とはちょっと違った頭のトレーニングをすることができるのがミラノサローネ。
So what’s next?

ミラノサローネでは、ロボットやさまざまなインタラクション、新しい技術的なものもたくさん見ましたが、私にとって、ミラノサローネで見つけた「So what’s next?」は、そうした、トレンドワード的な何かや、細分化されたデザイン領域などではなく、人間としての圧倒的な美意識と情熱でした。
シンプルに「いいものは、いい」ということかもしれません。
Webのプロジェクトでも、プロダクトデザインでも、社会課題解決のデザインでも、全ての意思決定におけるデザイナーの選択は重大な意味をもちます。自然への賛美や他者(ロボットも?)への尊敬、なによりデザイナー自身の強い想いと主体性はますます欠かせなくなるでしょう。
そうしたときに、全ての礎になるのが美意識であり、情熱。
そして背景や設計意図はどうあれ、最終型が直感的に「良い」と感じるか、「気持ちいい」と感じるかどうか。
「ミラノサローネに行きたい」と上申しつつも、実態がよくわからずに行ってみたというのが正直なところですが、「百聞は一見にしかず」で、やはり行ってみて初めてわかることがたくさんありますし、いくら言葉を尽くしたとしても、行ったことがない人に価値をわかってもらうのもまた難しいように思います。
デザイナーであれば、あるいはデザイン業界にいるのであれば、ぜひ機会を捉えて、その目で確かめに行くことをおすすめします。印象的だった展示を後編「2019年「ミラノサローネ」の見どころ Milano Design Week 2019[2]」で紹介していますので、そちらもぜひお読みください。
TipsとLinks
最後に、この記事を読んで、来年はミラノサローネに行ってみようかなと考えている方のために、少しのティップスを残しておきます。
ミラノサローネのために事前にやっておくべきこと
- 航空券の予約(理想は前年末頃までに。遅くとも1月中)
- ホテルの予約(理想は前年末頃までに。遅くとも1月中)
- ローフィエラ本会場に行く場合はチケットの購入(コンファメーションは印刷推奨)
- SuperStudioの入場登録(コンファメーションは印刷推奨)
- 必ず見たいと考えている展示はリストアップし、日程とルートを検討(雨天と晴れの日別をつくっておくと便利)
- 直前に有志によりつくられるマップなども探してダウンロード
- ミラノサローネ経験がある人からの情報収集
- 行列が予想される人気の展示は、VIPや関係者として入場できないか事前に根回しも
今回コンセントのメンバーはGoogleやwallpaperの展示などがあったPorta Venezia(ポルタ・ヴェネツィア)と呼ばれるエリアに宿泊しました。(Ibis Milano Centroというホテル)
ヨーロッパの他の都市同様、ミラノも中央駅(チェントラーレ)周辺はあまり治安がいいとは言えません。
ポルタ・ヴェネツィアのあたりは、チェントラーレにも歩いていくことができ、トルトーナ地区に行くにもローフィエラなど遠くに行くにも便利で、かつチェントラーレ周辺ほどの雑然とした感じはありませんでした。
予算が許すようであれば、ブレラ地区のMoscova駅周辺は、展示が多く集まっているだけでなく、雰囲気のよい店なども多数あり、ミラノサローネ常連の人たちの間でも人気のようでおすすめです。
【参考サイト】
ミラノサローネオフィシャルサイト
フォーリサローネオフィシャルサイト
Milano Salone Description
MODERNLIVING
superstudioのオフィシャルサイト
Brera Design District
Opficio 31
Ventura Project(Ventura Centrale)
- テーマ :