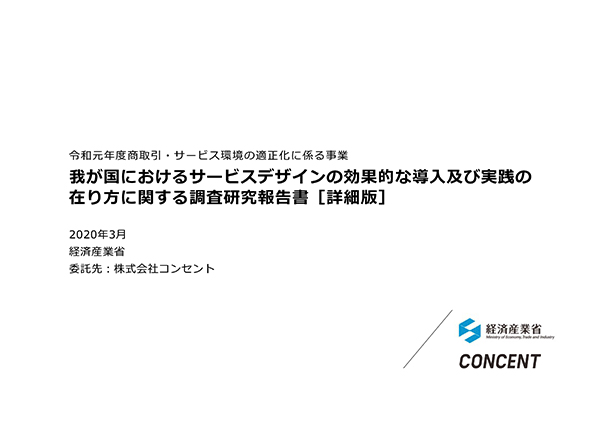サービスデザインによるイノベーション イノベーションのためのサービスデザイン(3)
- デザイン経営
- サービスデザイン
※本記事は、一般社団法人 行政情報システム研究所発行の機関誌『』2019年4月号に掲載の、長谷川敦士による連載企画「イノベーションのためのサービスデザイン」No.3「サービスデザインによるイノベーション」からの転載です(発行元の一般社団法人 行政情報システム研究所より承諾を得て掲載しています)。

1. サービスデザインによるイノベーション
前回まで、サービスデザインの考え方を紹介してきた。今回から、サービスデザインとイノベーションについて考えていきたいと思う。
サービスデザインアプローチによるイノベーションの例として、先に日本語版も刊行された、Service Design Networkが2017年に発行したレポート「Service Design Impact Report: Health Sector」から、スウェーデンの予防医療プログラムの成果を紹介しよう(文献1)。
図1:Service Design Impact Report: Health Sector
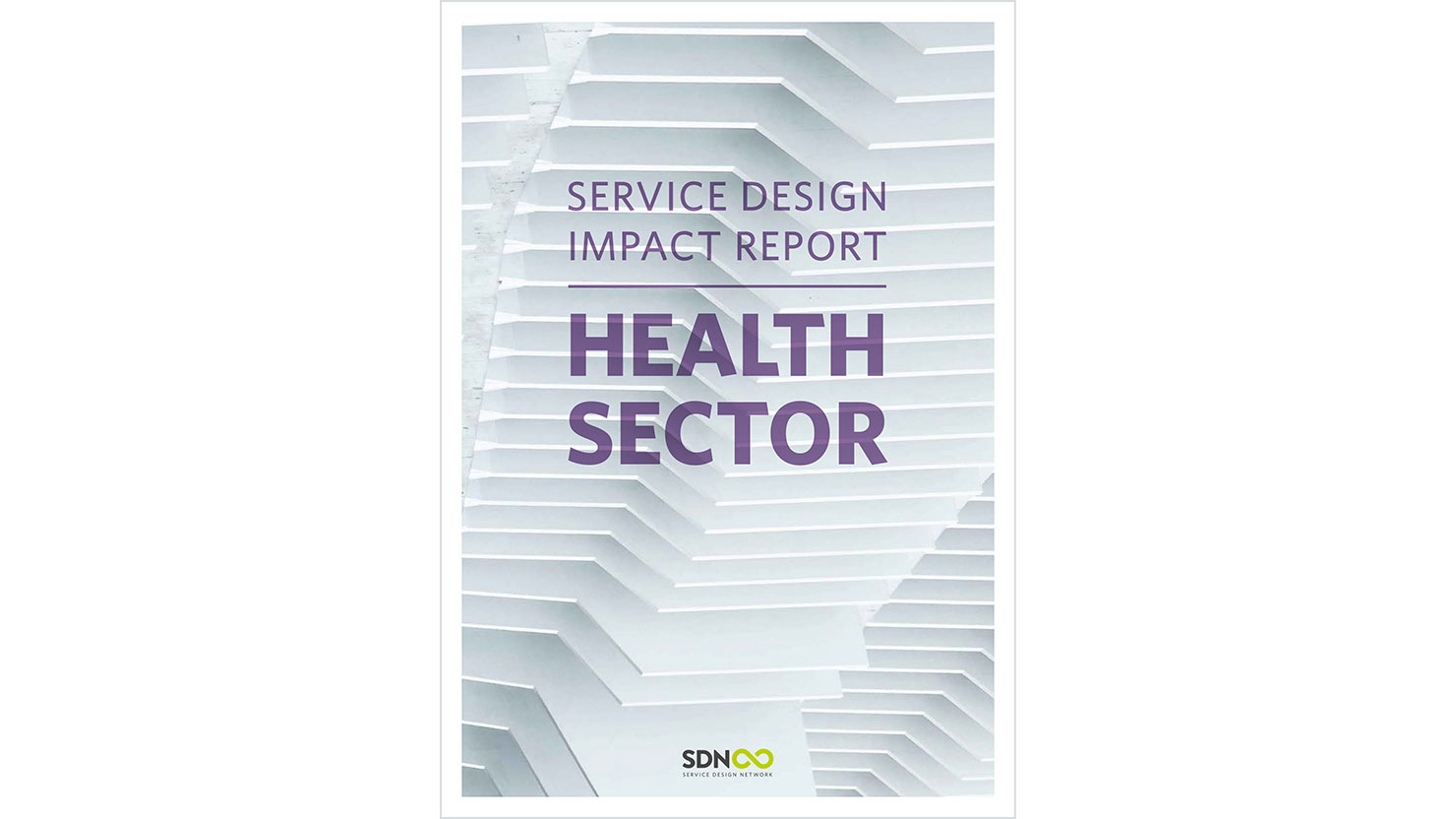
出典:Service Design Network, (2020年5月25日)
ガン予防検診案内
スウェーデン政府では、ガン罹病と死亡率の低下のために、国家ガン戦略を2009年に策定した。この戦略は国全体で長期的な視点で改善分野を明らかにするものである。そのなかで、予防は決定的に重要であると確認された分野の一つとなる。スウェーデン政府は自治体や地方ガンセンターと連携することを決定し、その後数年間におよぶ医療分野の専門家を含むプロジェクトチームによって国家プロジェクトが推進された。
このなかで、マンモグラフィーと婦人科検診の受診率をそれぞれ80%と85%まで向上させることと、プログラムが幅広い層からアクセスされやすくなることを目的としたプロジェクトが設置された。プロジェクトには、サービスデザインを専門とする「Transformator Design」、多文化コミュニケーション分野を得意とするマーケティングエージェンシー「Kapi」との協力により進められた。
スウェーデンの女性は国の2つのガン検診プログラムを受けることができる。23歳から64歳までの間に子宮ガン検診、そして40歳から74歳までの間に乳ガンの早期発見のためにマンモグラフィーを受けることができる。一般的な受診率は国際的に見れば高いものの、年齢や社会経済的なバックグラウンドによって大きな差が見られる。特に、30歳以下の若い女性、家庭と仕事をもつ多忙な中年女性、教育レベルが低く検診の知識や習慣が欠けている女性たちにおいて、受診率が低い傾向が見られており、これらの集団の受診が受診率の改善の大きな要因となる。また、文化や予防意識の異なる他国からの移住者も重要な対象者となる。
プロジェクト発足当初、スウェーデン政府の国家ガン戦略におけるプロジェクトの一つで行われた検診組織やその他の調査によってすでに以下の要因が受診の促進につながることがわかっていた。
- 検診の予約時間つきの案内状を送る
- 検診に来なかったり、スケジュールを変更した女性にリマインダーを出す
- 電話やオンラインサービスで簡単に予約の日時変更ができるようにする
- 病院において、個人に合わせた対応をすることで、ポジティブな体験ができるようにする
- 夜間に検診を行ったり、職場近くで検診を受けられるようにして、受診しやすさを向上させ、選択肢を増やす
また、この時期女性の主体的な検診を促進すべきであるという方針が設定された。スウェーデンのすべての女性は、検診プログラムに自由にアクセスすることができ、受診を動機づけられ、検診がなぜ重要なのかを理解しているべきであり、サービスは簡単で柔軟性があり安心できるものでなくてはならない。そして女性たちは長い期間プログラムを続けていく重要性を自ら理解している必要がある。
サービスデザインプロジェクトの実施
この状況で、サービスデザインプロジェクトが推進された。スウェーデンのさまざまな地域に住む女性90名への綿密なインタビューが行われ、彼女たちと共にどのように検診についてコミュニケーションしていくべきか、どういった案内状が出されるべきかが検討された。この結果、以下の実現すべきポイントが明らかとなった。
- 1.あらゆるルートから連絡できるようにする
その人が好む手段と言語で、検診機関と連絡が取れるようにする。検診を受けない人たちはデジタルサービスに抵抗感をもっていることがあり、電話によるコミュニケーションも重要となる。また、多くの人々が検診の案内のような重要な連絡は未だに従来のように手紙を通じてやってくると考えており、この状況に合わせる必要がある。もちろん、多言語に対応している必要がある。
- 2.共通のテンプレートを用いたコミュニケーションを行う
スウェーデンでは、多くの医療提供者がおり、その機関名や検診の案内もさまざまな形態がある。そのために、一人の女性の元に全く異なるデザインの子宮頸部細胞診の案内状とマンモグラフィーの案内状が届くということが起こってしまう。見た目のデザインに加えて情報提供のしかたを定めた共通のガイドラインとテンプレートを使用して、国が行う検診について、明確な同一性をつくり出すことが求められる。 - 3.より意欲を持たせるコミュニケーションを行う
情報は正しくあるべきだが、怖じ気づかせたりストレスを感じさせるものであってはならない。検診の受診は任意であるということを正しく伝えることによって、怖じ気づかせることなくより気楽に思わせることができるようになる。
こういったポイントに基づき、新しく案内状がデザインされた。この旧案内状と新案内状とをランダムに使ってテストが行われ、新案内状は明らかに効果があることが見出された。また、それだけでなく、この新しい案内状は、これまでに採用された新しい取り組みや手段と比べて、受診率に最も影響があることが判明した。
新しい案内状の改善点は、「女性たちを勇気づける」、「受診の目的とその利点を明確にする」、「よりわかりやすい言葉や文章を用いる」などであった。最終的にこの新しい案内状によって、検診プログラム受診率は特定のターゲット集団で最大20.6%向上する成果を上げた。
しかしながら同時に調査から、この新デザインはストックホルムの都市部の30歳以下の女性への効果が最も高かったものの、郊外エリアでは影響が低いことも判明した。これらの地域の住民は所得レベルと教育レベルが比較的低く、受診率も以前から低い地域であり、かつ他の地域と比べても移民の割合が高い地域でもあった。こういった状況に対応するためにプロジェクトはさらに調査を続けるとしている。
そういった課題があるとはいえ、この新案内状の成果を踏まえて、現在は地域ガンセンターとスウェーデン地方自治体協議会を通じてこのテンプレートがスウェーデン全体で用いられるようになっている。
サービスデザインによるイノベーション
以前に本誌(『行政&情報システム』)2017年4月号ので紹介した米NY市の給与所得税額控除申請支援プロジェクトと同様に、このプロジェクトでも、生活者の声を聞き共にデザインを行うことによって画期的な成果へとつながった。NYのケースも、導かれたボランティア組織の名称を変更するといった一見地味な施策が、生活者の視点と実際の行動とにマッチしていたことで成果に結びついている。これらは、イノベーションとは必ずしも奇をてらった施策である必要はなく、しっかりと生活者の視点に立っていることが最も重要であるということを教えてくれている。
技術的なイノベーションは、既存技術がなしえなかった高機能化が求められるが、サービスにおけるイノベーションは成果が得られるかどうかが最も重要なポイントであり、見た目の新しさではない。もちろん、だからといってちょっとした改善でよいことを最初から規定しているというわけではなく、これは我々がいかに身の回りのちょっとした改善機会を見過ごしているかということを示しているに過ぎない。その機会を発見するのがサービスデザインのアプローチであるということなのだ。
2. サービスデザインの推進体制
サービスデザイン推進のための人材
行政組織におけるデザインによるイノベーションの推進においては、さまざまな形態のプロジェクトチームが結成される。こんにち、行政サービスにおけるデザインチームの活動は新たなサービスの創出だけでなく、プロセスの変革、教育などにまで広がっており、活動の広がりにともなって行政内外両方の貢献者がみてとれる。
具体的には、以下の3パターンの関与の組み合わせとなる。
- 1.組織内デザイナー
フルタイム勤務の戦略策定に関わる組織内デザイナー。
組織のデザイン能力の開発や、特定のサービスのプロジェクト立案を担当。
いわゆるデザイン部門的な部門ではなく、一般の部門内でデザインを担当することに特徴がある。
- 2.行政内部の分野横断サービスデザイン部門
プロジェクトごとに組織内の他の部署と連携して活動を行う。
新規のプロジェクトの音頭を取ったり、組織内教育などの役割を担うこともある。
- 3.外部エージェンシー
プロジェクトごとのコンサルタントやデザインエージェンシー。
特に新規プロジェクトの立ち上げや、突発的な調査などの業務において用いられる。
海外の行政サービスの改革プロジェクトなどにおいても、上記の3パターンを組み合わせてプロジェクトが遂行されている。行政サービス改革で数多くの実績を上げているイギリスのGDS(Government Digital Service)などは2に該当し、先に例に挙げたスウェーデンのプロジェクトでは、3の外部エージェンシーとの協力体制でのプロジェクト遂行といえる。
サービスデザインの継続のために
GDSは、イギリス政府において主としてサービスの立ち上げを担っているが、それらのサービスは、その後各省庁などに引き渡されて運営されていく。その際は、上記1の組織内デザイナーが中心となって運用・改善が進められるが、一般の行政職員の意識改革と協力が必須となる。
すでに迅速なサービスの立ち上げについて一定の枠組みができあがっているGDSは、現在この運用と拡張の部分が課題であるとしており、GDSのデザインと標準化ディレクターのLouise Downe氏は以下の10の方針を提示している(文献2)。
サービス継続のための10の提言
- 1.デザイナーを雇え、そしてコミュニティをつくれ (Hire designers and build communities)
- 2.標準化が集権化につながるものであってはならない(Standardise don’t centralise)
- 3.組織的に展開できるようにする(Enable the network)
- 4.将来のデザインが可能なデザイン(Design something the future can design)
- 5.手を汚せ(Get your hands dirty)
- 6.未来に向かってデザインする(Design it forward)
- 7.なにをやっているのかを理解する(Understand how well you’re doing)
- 8.一緒に働けるようにする(Enable people to work together)
- 9.デザインのための代替組織をつくる(Create alternative structures of power)
- 10.批評的であれ(Be critical)
随所から自発的な参加を促すような意図が読み取れるが、サービスデザインの実施においては、いかにデザイナー以外の「一般の」メンバーがデザインアプローチに参加できるのかが重要となる。氏は、同時に「変革は永遠に“終わらず”、小さな改革が続く」とも言っているが、従来の「サービスを企画して、それを運用する」という考え方ではなく、「小さく立ち上げて改善を繰り返して育てていく」というサービスデザインのトレンドとも合致する。
またこのことは、こういった教育やモチベーション向上といったことを促す「カタリスト(変化を促す人)」という役割が特に組織内デザイナーやデザイン組織に求められている状況にも合っている。このあたりは、昨年Service Design Networkから刊行された「Design Thinking In-house: Design- Driven Innovation Labs」でも言及されている。この組織の変革については次回以降で取り上げよう。
図2:Design Thinking In-house: Design-Driven Innovation Labs
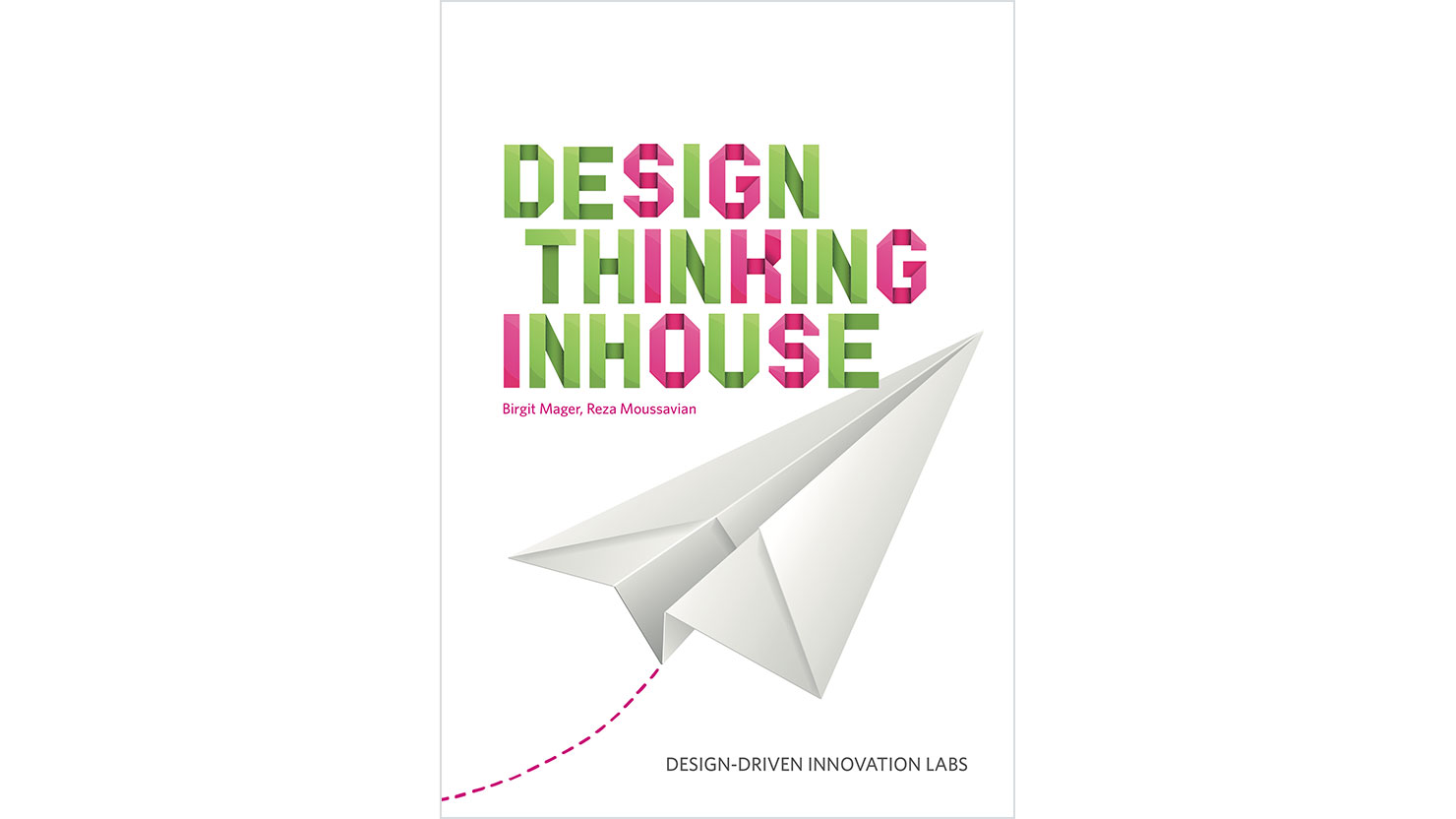
出典:Service Design Network, (2020年5月25日)
参考文献
- 1 , Service Design Network(2017)
- , Service Design Network(2016)
- , Service Design Network(2017)
- 一般社団法人 行政情報システム研究所, 行政&情報システム, vol. 53 No.2 通巻566号
- 2 Louise Downe,