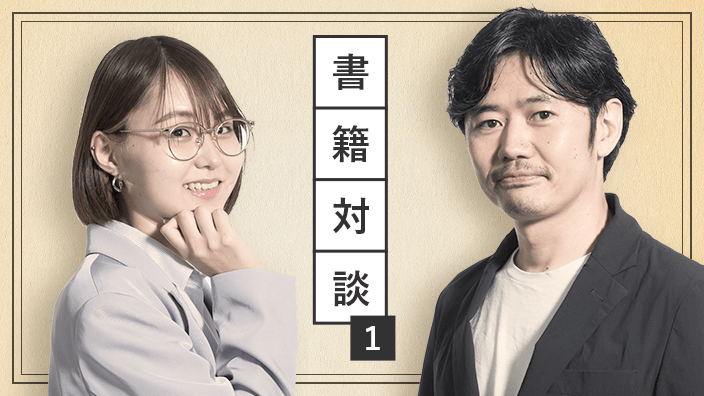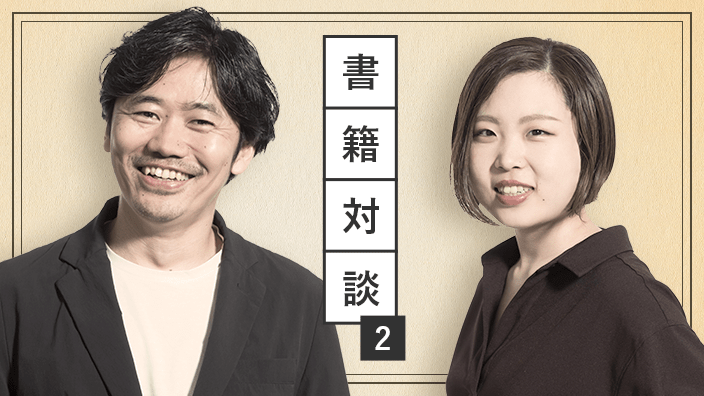永井玲衣さんとの哲学対話 そこで起きていたことをつかまえたい DESIGN AND PEOPLE SOCIAL CLUB vol.1
- コミュニケーションデザイン
- コンセントカルチャー
コンセントが刊行するデザイン誌『DESIGN AND PEOPLE』のイベントシリーズ「DESIGN AND PEOPLE SOCIAL CLUB」(通称:デザピー・ソシアルクラブ)。その初回として、誌面上でコンセント長谷川と対談を行った哲学者・永井玲衣さんによる哲学対話が開かれました。哲学対話とは、参加者みんなで問いを立て、対話を通して問いを深めていくもの。当日は、チームも職能も異なる12人のコンセントメンバーが集まり、日常の中の小さな疑問について、永井さんと共に対話を行いました。

本記事では、その対話の場で一体何が起きていたのかを考えてみたいと思います。
私は参加者としてその場に居合わせて、一部始終に関わっていました。しかし、哲学対話の当事者となったその場においては、客観的な視点や分析的な態度を手放していました。だから本記事を執筆するに当たり、記憶を手繰って、私自身に起きていたことを、自分の言葉によってあらためてつかまえる必要があります。
また断っておかなければいけないのは、本記事では当日の対話内容を詳しく言及していないということ、そして私の体験しか語ることができないということです。その理由とともに、これから私が体験した哲学対話を言葉にしていきます。
新しい私たち
長谷川:複数の人間でデザインを行っていくと、当たり前のこととしてそこには対話が必要になってきます。(中略)でも、最近僕が思うのは、逆なんじゃないかということ。(中略)僕らは仲良くなるためにプロジェクトをやっている——そう捉えたほうがいいなと最近気がついたんです。対話をすること自体が本質なのではないか。
永井:私にとって、哲学は対話をする理由なんですよね。(中略)人びとが「なんでだろう」と思っていることのもとに人が集える。集まった人たちの属性はバラバラでいいんです。バラバラのまま、でも集うことができる。
(「わからないからいつまでも」,『DESIGN AND PEOPLE Issue No. 1 デザインは主語じゃない』, p.48, コンセント, 2023)
哲学対話は、問いを立てることから始まります。参加者一人ひとりが日頃の生活の中で不思議に思うことを「問い」として提示し、当日はその中から多数決で選ばれた「“居心地がいい”ってどういうこと?」という問いについて、対話することになりました。
永井さんの哲学対話では、発言者が鳥のぬいぐるみを手にもち、次の発言者へと渡しながら対話を進めていきます。そこでの約束は、「よくきく」「偉い人の言葉を使わない」「結局人それぞれにしない」。
対話は、時にぬいぐるみが宙を舞うように軽やかに、時にコロコロと転がるようにぎこちなく、参加者の輪の中を巡ります。そして90分がたち、永井さんの合図で、結論も出ないまま唐突に終わりを迎えたのでした。


そこでどんなことが話されたのかを、私はここでは紹介しません。なぜなら、誰が何を話した、という事の顚末を解説しても、その場で起きていたことの実感を伝えることができないと思うのです。
手応えとして残るのは、そこに新しい私たちがいたという感覚です。
私たちは同じ会社で働く仲間であり、お互いにどんな人かを多少なりとも知っています。しかしあの場で私たちは、互いの言葉に耳を傾け、呼応しながら自分でも気付かなかった自分を、輪の中にひらいてしまっていたのではないかと思います。
あるメンバーは「人に言わない秘密を打ち明けてしまいそうになった」、また別のメンバーは「普段はしまっている大事なものを少し分けてもらえたような、それが聞いている人にとっても大事なものになっていくような」と感想を話しました。

対話の中で、無防備で新しい私になり、新しい“私たち”を再発見したこと。それこそが、あの場だから立ち上がってくる意味だったように思います。永井さんは「哲学は対話をする理由」と言います。私たちはまさに「問い」を理由に、新しい私たちのための場を、共にかたちづくっていたのです。
流れる、流される
その場の中で、私は不思議な心地よさを感じていました。
それは、お互いをある程度知っていることによる安心感や、心理的安全性といった言葉だけでは説明できない、より身体的な感覚です。
発言者が変わるたびに、一つのテーマが深まることもあれば違うテーマへとそれていくこともある。私の発言もまたその流れの中にあり、そこからどう流れていくのかをコントロールすることができない。この不自由ともいえる状況に心地よさを感じました。
それは裏返せば、自分を、他者を、環境をコントロールすることによって効率化された日々の生活とは異質な時間が、そこには流れていたということです。




他者の言葉を「よくきく」ことによって私の中に何が起こるかは、他者がトリガーである以上、私にコントロールすることはできません。私の言葉も、他者に「よくきかれる」ことによって、私の意図を裏切っていきます。やっとつかめたと思ったものが、かたちを変え指の間を擦り抜けていくような流動的な時間。だから対話は不安定で、歯がゆい……。
ではなぜそんな状況が心地いいのかといえば、誰がコントロールするでもなく、みんなで同じ状況をシェアできている感覚が私にはありました。参加者みんなで「問い」という不安定なイカダに乗り、一緒に川に流されているような。その楽しさも、しんどさもひっくるめて分け合えているような。
しかし、これはあくまで私が感じたことだと付け加えなければなりません。ままならない対話を通じて、みんなでその場を共有している感覚とともに、そこにいる一人ひとりは決してイコールにはならない他者なのだという事実もまた、私の身に迫りました。だから私は結局、私の体験を通してしかこの状況を語ることができないのです。
私たちは同一ではないのに、お互いをコントロールしないまま、その場を共有することが(少なくとも私はそう信じることが)できた。
そこに何があったのかと振り返るときにようやく、私は永井さんが哲学対話をケアと呼ぶことの意味をつかまえられるような気がします。
哲学対話は、ケアである。セラピーという意味ではない。気を払うという意味でのケアである。哲学は知をケアする。真理をケアする。そして、他者の考えを聞くわたし自身をケアする。立場を変えることをおそれる、そのわたしをケアする。あなたの考えをケアする。その意味で、哲学対話は闘技場ではあり得ない。
(永井玲衣, 『水中の哲学者たち』, p.97, 晶文社, 2021)
その先にある問い

最後に、ここにもう一つの「問い」を立ててみたいと思います。
あの日、会場であるamuに着くと、テーブルを囲んで参加者分の椅子が整然と並べられていました。事前予約制の席だけが、あの不安定なイカダには用意されていたのです。この光景の意味を、今でもずっと考えています。
永井さんの哲学対話は、時間が来たらそこでおしまい。「あえて」まとめず、結論も出さずに終わります。永井さんがそこに込めた思いに応えるならば、私が私自身に、その先を問わなければなりません。私たちのイカダを運んでいた川は、じきに日常の海へと流れ出ていきます。そこに身を任せられる心地よさはなく、荒れ狂う大波にイカダは脆くも崩れ去り、無数の人々と共に投げ出されるでしょう。
では、無数の私たちはどのように、同じ海を生きることができるのでしょうか。あの川の流れとともにあった、柔らかで豊かな時間を、どのように分かち合うことができるのでしょうか。
永井さんは、哲学対話を人工的なものだと言います。自然発生的には生まれてこない、ある特殊な状況でようやく現れ得るのだと。ならば、私たちは人工的な何かを頼りに、先の問いを共に考えることだってできるかもしれません。そしてその人工的な何かって、もしかしてデザインと呼べるものなんじゃないかと、デザインの現場に身を置く私は考えています。
おわりに
なんとも歯切れの悪い、曖昧な状態で本記事を結ぶことになってしまいました。しかし、この曖昧な状態を誰かと共有したい、一緒に考えたいという欲求が自分の中にあるのだということを、私は哲学対話を通してあらためて知ることになりました。
永井さんは、ものすごく一緒に考えてくれる方でした。対話が始まるや否や、耳から入ってくる言葉に全神経を集中させるようにうつむきながら一点を見つめる姿に、きっと参加者の誰よりも永井さんは考えている……これが「よくきく」ということなのか……と妙に納得してしまったのでした。
私の言葉をこんなにも聞いてくれる人がいるのだと、素朴なうれしさがそこにはありました。永井さん、本当にありがとうございました!次回の哲学対話も心待ちにしています。
デザピー・ソシアルクラブは、社内外交流イベントです。読者の皆さまをお誘いするかもしれませんので、コンセントSNSのフォロー&チェックをよろしくお願いします!

写真/栗原 論
永井玲衣さんとコンセントメンバーによるアフタートークの動画(約5分)

- テーマ :